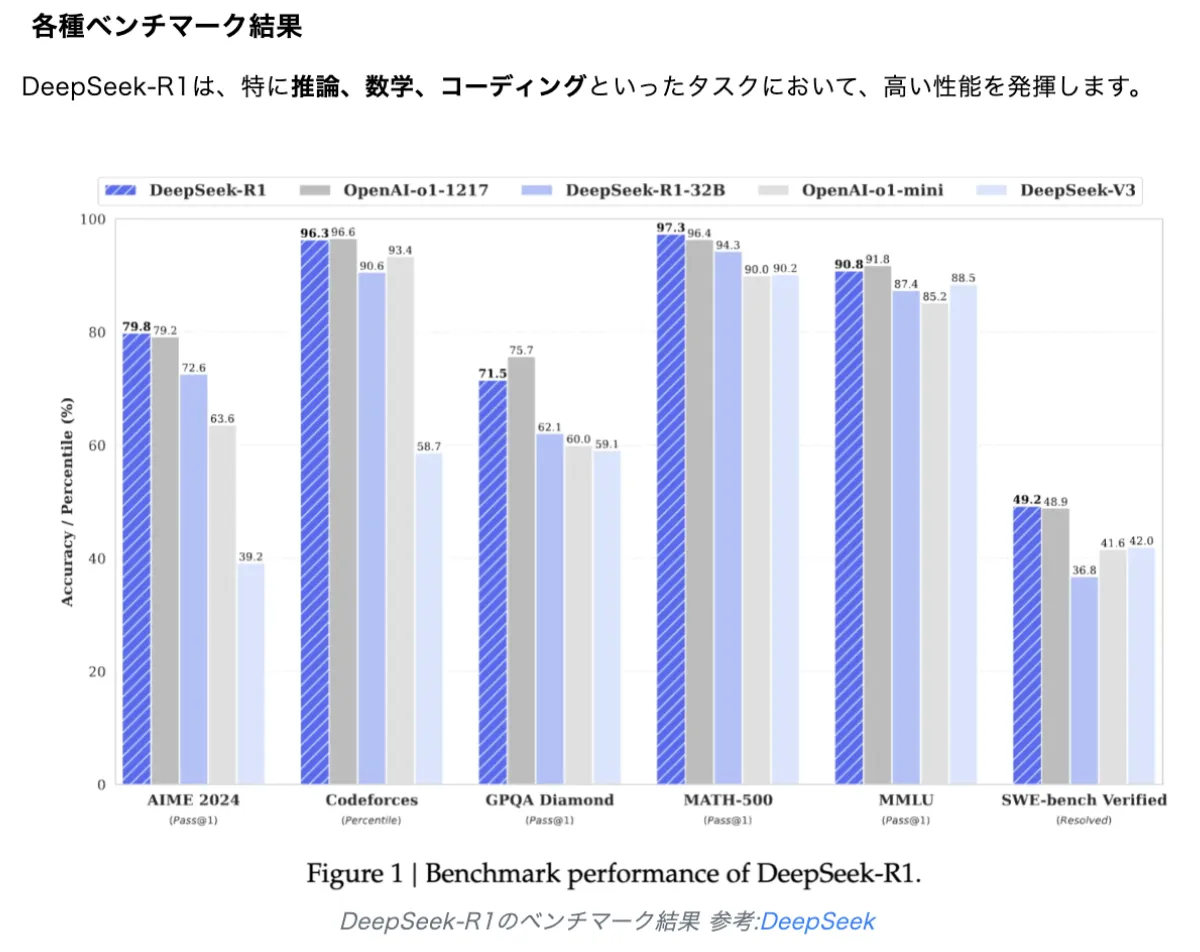【GPU活用で進化する生命科学研究】慶應大学とNTTPCの取り組みインタビュー
AI総合研究所は、慶應義塾大学 先端生命科学研究所におけるGPU活用に関するインタビューの実施をサポートしました。 本記事では、その様子や背景についてご紹介します。

データ駆動型生物学が直面した「計算の壁」
21世紀の生物学がデータ駆動型へとシフトする中、荒川教授の研究室では、クマムシやクモの糸といった生物が持つ優れた機能を解明するため、日々膨大なデータを解析しています。
特に、DNA塩基配列をリアルタイムに読み解くゲノム解析や、AI(大規模言語モデル)を用いて新しいタンパク質を設計する最先端の研究では、従来の計算基盤ではGPUのメモリ(VRAM)が不足し、研究のスピードを左右する大きなボトルネックとなっていました。
NTTPCのソリューション導入と期待される効果
この課題を解決するため、今回NTTPCから導入されたのが、NVIDIAの最新アーキテクチャ「Hopper」を採用したH100 NVL GPU搭載サーバーです。NTTPCは、ウェブサイト上で迅速に概算見積もりが得られるスピード感と価格の妥当性が評価され、導入に至りました。
この新たな計算基盤により、以下の効果が見込まれています。
- 研究時間の大幅な短縮: ゲノム解析や分子シミュレーションにかかる計算時間を大幅に短縮し、研究開発サイクル全体の効率化を実現。
- 大規模AIモデルの活用: これまでメモリ不足で困難だった大規模言語モデルの構築・運用を可能にし、新機能を持つタンパク質の合理的設計(ラショナルデザイン)を加速。
社会実装への展開と今後の展望
荒川教授の研究は、すでに社会実装に向けた取り組みに結びついています。たとえば、Spiber株式会社と共同で人工クモ糸素材「Brewed Protein™」の開発を行い、製品化まで進められています。膨大なゲノムデータと物性情報を解析することで、「洗濯しても縮まない」といった特性を持つ配列が見出され、それが素材設計に活用されました。
本取り組みの詳細については、以下の導入事例インタビューをご覧ください。
【GPU×研究】生命科学研究を加速させるGPUコンピューティング ~NVIDIA H100 NVL搭載サーバーの導入で、大規模なゲノム解析や分子シミュレーションを後押し~