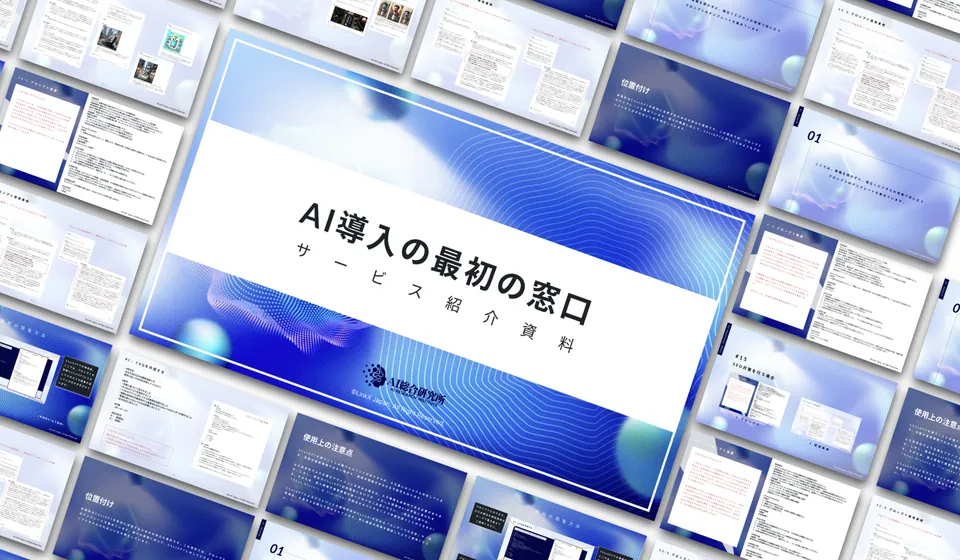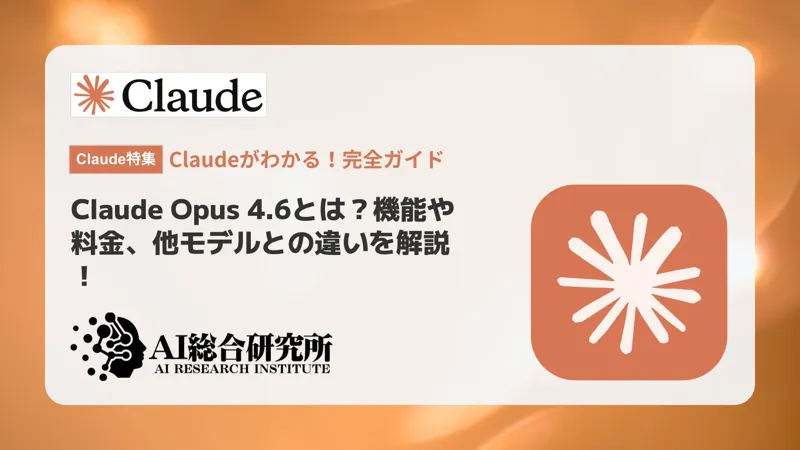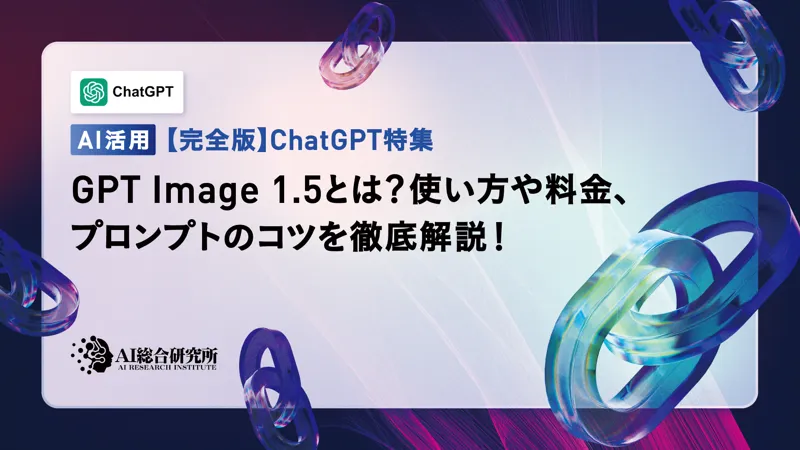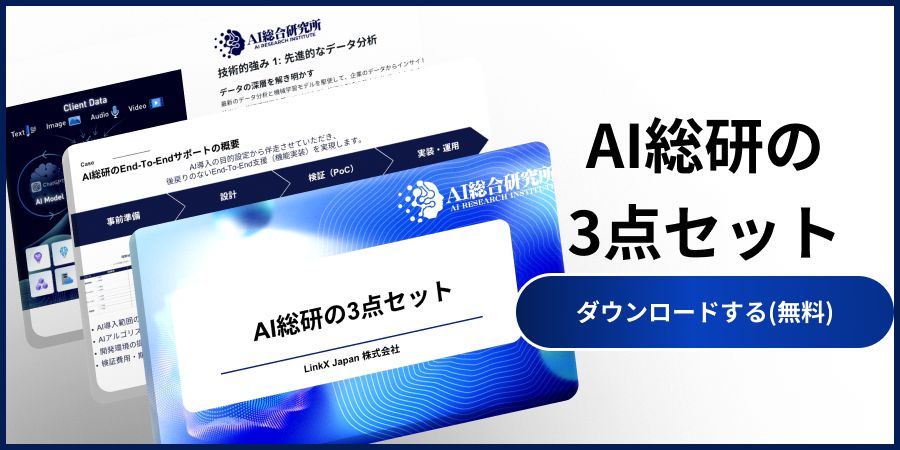この記事のポイント
ホームページ作成とは、情報発信や集客を目的としたWebページの設計・公開プロセスのこと。
Webサイトとの違いは本来あるが、日本語ではほぼ同義で使われている。
作成手段はHTML、CMS、ノーコード、AI活用型などがあり、目的と体制に応じて選ぶことが重要。
AI Marketerは、コンテンツ作成・ABテスト・高速配信をAIで支援する次世代ツール。
見た目だけでなく、更新性・モバイル対応・改善体制まで考慮して構築・運用するのが成功の鍵。

Microsoft MVP・AIパートナー。LinkX Japan株式会社 代表取締役。東京工業大学大学院にて自然言語処理・金融工学を研究。NHK放送技術研究所でAI・ブロックチェーンの研究開発に従事し、国際学会・ジャーナルでの発表多数。経営情報学会 優秀賞受賞。シンガポールでWeb3企業を創業後、現在は企業向けAI導入・DX推進を支援。
ホームページは、企業や個人がオンライン上で信頼や成果を築くための重要な接点です。
近年では、CMSやノーコードに加え、AIを活用したホームページ作成ツールも登場し、誰でも短時間でプロ品質のWebサイトを構築できる時代になりました。
この記事では、ホームページ作成の基本から手法の違い、費用感、よくある課題、そしてAI活用型の新手法「AI Marketer」の活用ポイントまでを、実務目線でわかりやすく解説します。
1. ホームページ作成とは?
ホームページ作成(制作)とは、企業や個人が情報発信や集客を目的にWebページを構築・公開することです。
インターネット上に自社の情報やサービス内容を掲載し、閲覧者との接点をつくるための手段として「ホームページ作成」は長年にわたり活用されてきました。
近年では、単なる情報掲載にとどまらず、問い合わせ獲得、商品購入、資料請求、採用応募など、明確な目的を持った構成が求められています。
かつてはHTMLやCSSを手打ちで記述する必要があり、制作には高度な専門知識が必要でした。しかし現在では、CMS(コンテンツ管理システム)やノーコードツール、さらにはAIを活用したページ作成支援サービスの登場により、誰でも短時間でプロ品質のホームページを構築できる時代になっています。
その中でも、AIを活用してページ構成やコンテンツ生成、LP最適化まで自動化する「AI Marketer」のようなツールは、これまでWeb制作に関わったことのないビジネス担当者でも本格的なページ運用を可能にする、新しい選択肢となっています。
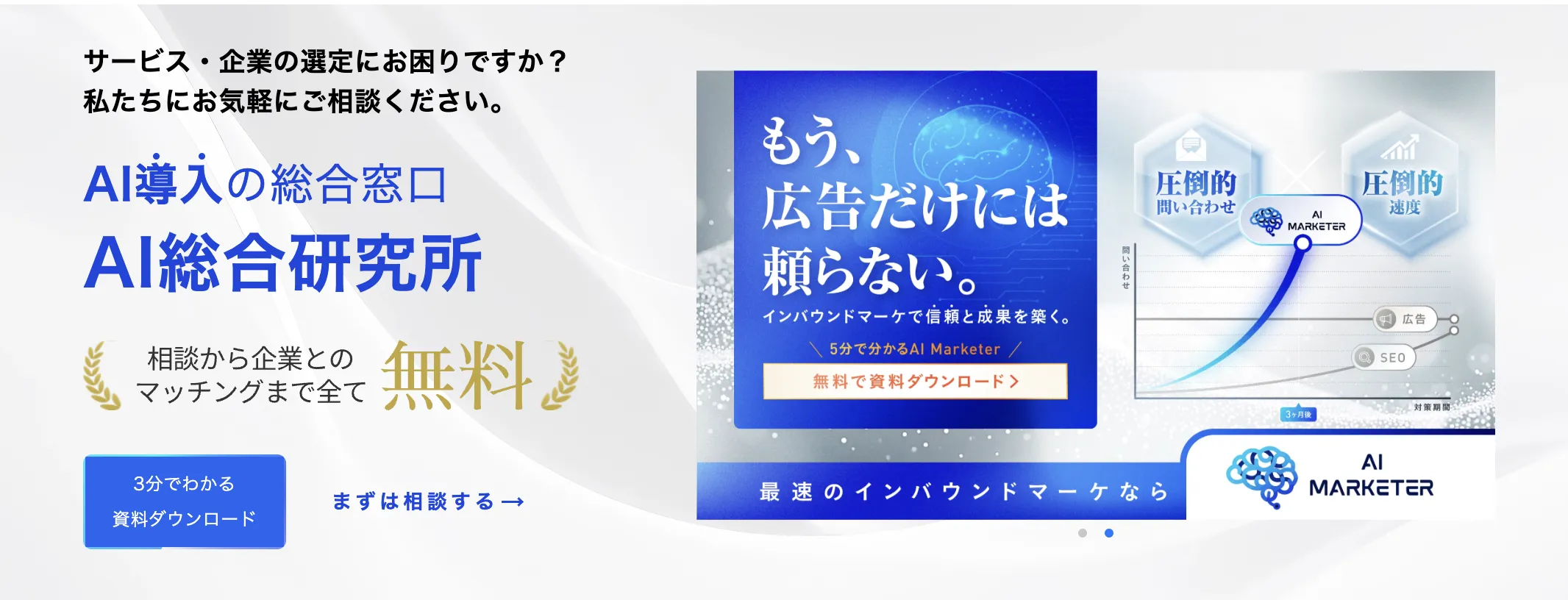
弊社ホームページファーストビュー
2. ホームページとWebサイトの違い
「ホームページ」と「Webサイト」は、日常会話ではしばしば同じ意味で使われますが、厳密には異なる概念を指します。ここでは、それぞれの言葉の本来の意味と、日本での使われ方の違いについて整理します。
本来の定義
-
ホームページ(Homepage)
Webブラウザを起動したときに最初に表示される「入り口のページ」や、Webサイト内のトップページを意味します。 -
Webサイト(Website)
複数のWebページで構成される情報の集合体。トップページ、下層ページ、ブログ記事、フォームなどを含む、全体の構造を指します。
日本における実際の使われ方
日本語では、「ホームページ」という言葉がWebサイト全体を意味するものとして広く浸透しています。特にビジネスの現場や行政の説明文では、「会社のホームページを作る」「ホームページからお問い合わせください」など、実質的にWebサイト全体を指して使用されています。
3. ホームページ作成の主な目的と種類
ホームページは単に情報を載せるだけのものではなく、目的に応じた設計と運用が求められます。ここでは、企業や個人がホームページを作成する主な目的と、その種類を紹介します。
主な目的
-
情報発信
企業概要、製品・サービスの紹介、会社の方針などを対外的に公開するために活用されます。 -
信頼性の確保・ブランディング
名刺代わりとなるようなWebサイトの存在は、企業や個人の信頼性を高め、認知の向上にもつながります。 -
問い合わせ・資料請求の獲得
フォームや電話・メール窓口を設け、見込み客との接点を持つ重要な役割を担います。 -
売上・コンバージョンの獲得
EC機能を持つサイトや、ランディングページ(LP)を通じて、商品の販売や契約につなげます。 -
採用・人材獲得
企業文化や社員インタビュー、募集要項などを掲載することで、求職者への訴求力を高めます。
ホームページの主な種類
| 種類 | 概要と活用目的 |
|---|---|
| 企業サイト | 会社紹介、事業内容、IR情報などを掲載 |
| サービスサイト | 特定の製品やサービスに特化し、申し込みや資料請求を促進 |
| ECサイト | 商品をオンラインで販売。カート機能や決済機能を備える |
| 採用サイト | 求職者向けに会社の魅力を伝える専門サイト |
| ブログ・オウンドメディア | SEOや情報発信を通じて集客・ブランド構築を図る |
| LP(ランディングページ) | 広告やキャンペーンに特化した1ページ完結型の訴求ページ |
| ポートフォリオ | デザイナーやエンジニアが自身の作品やスキルを紹介する個人サイト |
目的によって構成や必要な機能が異なるため、最初に何のためにホームページを作るのかを明確にすることが、成功への第一歩です。
4. ホームページ作成に必要な基本要素
ホームページを作成するには、単にページをデザインするだけでなく、公開・運用に必要な技術的および構成的な要素を理解しておくことが重要です。ここでは、一般的なホームページに共通する基礎的な構成要素を紹介します。
① ドメインとサーバー
- ドメイン:ホームページの住所にあたる部分。例:
example.com。独自ドメインを取得することで、信頼性やブランド力が向上します。 - サーバー:ホームページのデータを格納する場所。レンタルサーバー、クラウド、VPSなどの選択肢があります。
② コンテンツ(文章・画像・動画)
- ユーザーに伝えたい情報をテキストでわかりやすく整理します。
- 製品写真、図表、動画などのビジュアル要素を組み合わせて訴求力を高めます。
- ブログや更新情報など、定期的に更新できるコンテンツも重要です。
③ デザインとUI/UX設計
- 見やすく使いやすいデザインは、ユーザー体験に直結します。
- スマホでも見やすいレスポンシブ対応は必須。
- フォントサイズや配色、ボタンの配置など、ユーザー目線で構成することが求められます。
④ SEOとパフォーマンス最適化
- タイトルタグやメタディスクリプションの設定、画像の代替テキスト(alt属性)などのSEO施策が必要です。
- ページ表示速度はユーザー満足度や検索順位にも関わるため、軽量設計やCDNの活用が有効です。
⑤ フォームやCTA(Call to Action)
- お問い合わせや資料請求のフォーム、購入ボタンなど、ユーザーの行動を促すCTAが必要です。
- 明確な導線を設計し、コンバージョン率(CVR)を意識した構成が重要です。
5. ホームページ作成の方法別比較
ホームページ作成にはさまざまな方法があり、技術力・目的・予算に応じて選択肢が変わります。ここでは、代表的な4つの方法を比較し、それぞれの特徴と適したケースを解説します。
| 方法 | 特徴 | 向いている人・ケース |
|---|---|---|
| HTML/CSSコーディング | すべてを手動で記述。柔軟性は高いが難易度も高い | エンジニア、完全な自由設計を求める場合 |
| CMS(WordPressなど) | 管理画面でページ作成が可能。拡張性に優れる | 一般企業、ブログ、情報更新が多いサイト |
| ノーコードツール | ドラッグ&ドロップで簡単作成 | デザイナー、予算が限られる個人や小規模事業者 |
| AI活用型(AI Marketer) | AIがコンテンツ生成・デザイン・ABテストも支援 | マーケ担当者、スピード重視のチーム |
HTML/CSSでの手作業
HTML・CSS・JavaScriptを直接書いて作成する方法です。最大限の自由度がある反面、専門知識が必須で、更新や保守の手間も大きくなります。
CMS(コンテンツ管理システム)
WordPressを代表とするCMSは、ブログや企業サイトで多く使われています。豊富なテーマやプラグインにより、非エンジニアでも柔軟なカスタマイズが可能です。ただし、セキュリティ対策や運用管理は必要になります。
ノーコードツール
STUDIO、Wix、ペライチなどのサービスは、コーディング不要で直感的にページを作成できるのが魅力です。テンプレートベースでスピーディに立ち上げたい人に向いています。
6. 技術選定の考え方とJamstack・ヘッドレスCMSの選択肢
ホームページをどの手段で作成するかを決める際には、目的やチーム体制、今後の運用フローに応じた「技術選定」が欠かせません。
たとえば、
- 頻繁なコンテンツ更新が必要ならCMSが適していますし、
- 表示速度やセキュリティを重視するならJamstack構成が有力な選択肢になります。
最近では、APIベースで柔軟に構成できるヘッドレスCMS(Contentful、Strapiなど)と、CDNによる高速配信を得意とする**Jamstack(JavaScript + API + Markup)を組み合わせた構成も主流です。
こうした構成は、フロントエンドとコンテンツ管理を分離できるため、マーケ担当と開発チームの役割分担がしやすく、運用効率も高まります。
より詳しくは、下記の記事で解説しています。
このような技術的選択肢を知っておくことで、自社に合ったホームページ作成の方向性がより明確になります。
6. AI MarketerによるAI活用型ホームページ作成

AI Marketer
従来のホームページ作成には、「コンテンツを書く」「デザインを整える」「A/Bテストを回す」など、複数の工程と専門知識が必要でした。AI Marketerは、これらの工程を一貫してAIで支援し、非エンジニアやマーケティング担当者でも成果に直結するページを短時間で構築できる革新的なツールです。
主な特長とできること
| 機能 | 内容とメリット |
|---|---|
| コンテンツ自動生成 | AIが商品やサービスに最適なコピーを提案・執筆 |
| デザインテンプレート最適化 | UI/UXに基づいた構成を自動反映。見やすく訴求力が高い |
| A/Bテスト自動実行と学習 | クリック率やCVRのデータをもとに、自動で改善を繰り返す |
| フォームやCTAの最適配置 | ユーザー行動を分析し、離脱を減らす導線を提案 |
| Jamstackベースの高速配信 | 静的ファイル+CDNにより、モバイルでも高速な表示を実現 |
| ヘッドレスCMS | CMSの中でもヘッドレスを採用。AIが学習しやすくモダンなサイトに |
なぜAI Marketerなのか?
- スピード:手作業なら数日〜数週間かかる構築・改善作業が、AIにより数時間単位で完了。
- 専門知識不要:HTMLやSEOの知識がなくても、直感的な操作でプロ品質のページが完成。
- 改善に強い:作って終わりではなく、AIが「結果が出るページ」へと継続的に育てていく。
AI総合研究所は企業のLP作成、Webサイト制作、SEO対策などを手掛けており、AI Marketerを活用した実績も豊富です。お気軽にご相談ください。
7. ホームページ作成の費用と期間の目安
ホームページ作成にかかる費用や期間は、制作方法・規模・外注の有無によって大きく異なります。ここでは、代表的な3パターンに分けて、目安となるコストと制作スケジュールを紹介します。
① 制作会社に外注する場合
| 項目 | 内容・相場感 |
|---|---|
| 初期費用 | 30万〜1000万円程度(ページ数や要件による) |
| 制作期間 | 1〜2か月(要件定義・デザイン・実装含む) |
| 継続費用(保守) | 月5,000円〜数万円(サーバー、CMS更新など) |
- メリット:プロ品質、提案力がある、丸投げ可能
- デメリット:費用が高く、柔軟な更新はやや困難な場合あり
② CMS・ノーコードツールで自作する場合
| 項目 | 内容・相場感 |
|---|---|
| 初期費用 | 数千円〜3万円(テンプレートやテーマ代) |
| 制作期間 | 1日〜2週間(習熟度により変動) |
| 継続費用 | 月1,000円〜3,000円(ドメイン・サーバー代) |
- メリット:安価、スピード対応、柔軟な更新が可能
- デメリット:デザインやSEOに工夫が必要、初期設定に手間
③CMS +会社に外注する場合
| 項目 | 内容・相場感 |
|---|---|
| 初期費用 | 30万〜100万円程度(ページ数や要件による) |
| 制作期間 | 1〜2か月(要件定義・デザイン・実装含む) |
| 継続費用(保守) | 月5,000円〜数万円(サーバー、CMS更新など) |
- メリット:プロ品質、提案力がある、丸投げ可能
- デメリット:費用が高く、柔軟な更新はやや困難な場合あり
- AI Marketerを併用することで、コンテンツ生成やABテストも自動化可能
費用を抑えるコツ
- ページ数を最小限にしてスタートし、後から拡張する
- 初期はテンプレートを活用し、構成に集中する
- AIツールを併用し、制作と改善の内製化を目指す
いずれにしても、目的に合わせた施策と十分な技術を持ったパートナーを選ぶことが、成功のカギとなります。
8. よくある課題と失敗を防ぐポイント
ホームページ作成では、見た目の良さや立ち上げスピードに目を奪われがちですが、成果につながらない構成になってしまうケースも少なくありません。ここでは、よくある失敗パターンと、それを防ぐための実践的なポイントを紹介します。
① 見た目だけで満足してしまう
- 洗練されたデザインでも、目的(問い合わせ・資料請求・購買など)が明確でなければ効果は限定的です。
- → CTA(行動喚起)の明確化、ユーザー導線の最適化が重要です。
② 運用・更新体制を考慮していない
- 外注したものの、更新のたびに依頼が必要で運用コストが増大。
- CMSやAIツールで自社運用のしやすさを確保しておくことがカギです。
③ スマホ対応・表示速度を軽視
- モバイル閲覧が主流の今、スマホで崩れるデザインや遅い表示は大きな離脱要因に。
- レスポンシブ対応とページスピード最適化は必須です。
④ コンテンツの中身が不明確
- 見た目は整っているが、「誰に」「何を」伝えるかが曖昧だと、成果につながりません。
- ペルソナを明確にし、一貫性のあるメッセージ設計を行いましょう。
⑤ 分析と改善をしない
- 公開して終わりではなく、「どのページが読まれているか」「どのCTAが押されているか」を確認することが重要です。
- AIを活用して定量的なデータを収集し、PDCAサイクルを回すことが成功のカギです。
9. まとめ:目的に応じた手段を選び、AIの力も積極的に取り入れる
ホームページ作成とは、単にWeb上に情報を載せるだけでなく、ユーザーに行動してもらうための仕組みを設計・運用することです。ビジネスの目的やターゲットによって、必要な構成や最適な制作手段は異なります。
従来のHTMLコーディングやCMS、ノーコードツールに加えて、AIを活用したホームページ作成という新たな選択肢が登場しています。その代表例である AI Marketer は、AIによるコンテンツ生成やLP最適化、Jamstackによる高速配信を実現し、少ないリソースでも成果を出せる環境を提供しています。
制作手段は目的によって選び、作って終わりではなく「改善し続ける仕組み」をいかに構築できるかが、今後のWeb運用の成否を分けるポイントです。
AI総合研究所では、企業のAI活用、LP作成、Webサイト制作、SEO対策などを手掛けており、AI Marketerを活用した実績も豊富です。お気軽にご相談ください。
AI導入でお悩みの方へ